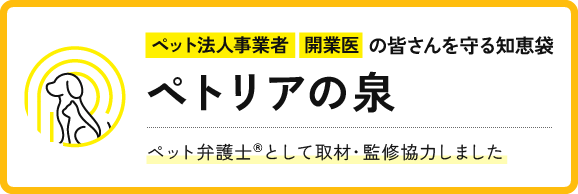動物病院トラブル裁判例のご紹介①

かつて昭和の時代は,獣医療過誤に関する裁判で,獣医療過誤が認められることは稀で,過誤が認められたとしても,ペットの飼い主に対し認められる慰謝料はわずか数万円にすぎませんでした。
しかし,最近の裁判例では,数十万円の慰謝料(それでも少ないとイチ飼い主としては当然思いますが)が認められる裁判例が出てきており,慰謝料の額は増加傾向にあるといえます。もっとも,賠償額が少ないとしても,裁判が提起されること自体,院長・スタッフ一同に大きな精神的負担がかかります。また飼主様の信頼を失い,さらには,何らかのきっかけで近隣住民の間に裁判沙汰になったことが広まれば,病院経営に著しいダメージを与えることは想像に難くありません。
地域に根差した動物病院経営を行うには,トラブルを避ける知恵と対策が必要といえるでしょう。
そこで,本記事では,飼い主様との間で起きた裁判例を紹介します。
真依子ちゃん事件(犬の糖尿病治療で,インスリンの投与を怠った獣医師の賠償責任を認めた裁判例 東京地裁平成16年5月10日判決 判例時報1889号65頁)
(事案)
AさんとBさんは日本スピッツ犬(真依子ちゃん)を飼育していましたが,平成14年12月28日,受診した動物病院で高血糖を指摘され,インスリンの投与を勧められたことから,かかりつけのY動物病院を受診し,翌日からY動物病院に入院しました。
入院中,食事療法等は行われたが,インスリンの投与は行われなかった結果,翌年1月3日,真依子ちゃんは死亡してしまいました。
AさんとBさんは,必要な治療が行われなかったとして,Y動物病院の担当獣医師C及びDに対して,損害賠償請求(民法415条・709条)訴訟を提起しました。
(判旨の概要)
⑴「担当獣医師のC及びDは,遅くとも12月30日の診察開始時の段階で,食事療法や運動療法のほか,本件患犬の状態を監視しながら,輸液療法及びインスリン両方を行い,重炭酸塩療法の実施を検討すべきであったというべきである。」として,12月30日の診察開始時の段階で行うべきインスリンの投与をしなかった過失,すなわち,C及びDの過失による不法行為に基づく損害賠償責任を認めました。
⑵ 慰謝料について,裁判所は以下のように述べ,AさんBさんに各30万円の慰謝料を認めました。
「犬をはじめとする動物は,生命を持たない動産とは異なり,個性を有し,自らの意思によって行動するという特徴があり,飼い主とのコミュニケーションを通じて飼い主にとってかけがえのない存在になることがある。」
「原告らは,結婚10周年を機に本件患犬を飼い始め,原告Aの高松への転勤の際に居住した社宅では,犬の飼育が禁止されているところを会社側の特別の許可を得て本件患犬を飼育したほか,その後の東京への転勤の際には本件患犬の飼育環境を考えて自宅マンションを購入し,本件患犬の成長を毎日記録するなど,約10年にわたって本件患犬を自らの子供のように可愛がっていたものであって,原告らの生活において,本件患犬はかけがえのないものとなっていたことが認められる。」
「また,原告らは,以前に飼育していた犬が病死したことから,本件患犬を老衰で看取るべく(スピッツ犬の寿命は約15年である。),定期的に健康診断を受けさせるなどしてきたにもかかわらず,約10年で本件患犬が死亡することになったものであって,本件以降,原告Bがパニック障害を発症し,治療中であることからみても,原告らが被った精神的苦痛が非常に大きいことが認められる。」
などと述べ,
「原告らが被った精神的損害に対する慰謝料は,それぞれ30万円と認めるのが相当である。」と判示しました。
(コメント)
ペット死亡事故の慰謝料はせいぜい数万円と言われていた中で,一人当たり30万円の慰謝料を認めたことで,マスコミにも取り上げられ,獣医療過誤の裁判例が増えたきっかけともいえる裁判例です。
動物病院側としては,獣医療技術の向上はもとより,インフォームドコンセントを徹底してトラブルを避ける,万が一トラブルになっても,自分たちの診療に落ち度がないことをしっかり説明できるようにカルテの記載を次充実させるなど,獣医療過誤訴訟の対応まで視野に入れた診療体制を整えておくことが大事でしょう。