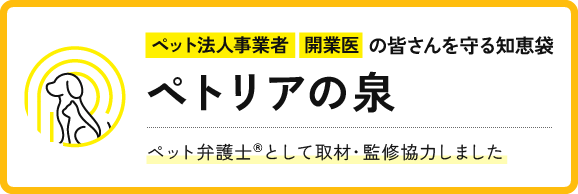動物病院におけるペットの医療事故について ペット医療事故の判例から解説

目次
1. 獣医師の法的責任

⑴ 動物病院と飼い主さんとの間の法律関係
飼い主が,獣医師にペットの治療を依頼することにより,獣医師と飼い主との間には,ペットの治療を内容とする診療契約が成立します。この診療契約は,民法上,「準委任契約」(民法656条「法律行為でない事務の委託」)に該当する,と考えられています。
⑵ 獣医師の法的義務
獣医師は,準委任契約である診療契約に基づいて,飼い主及びペットに対して「善管注意義務」(民法644条)を負います。具体的な診療行為が,この善管注意義務に違反していたかどうかは,「一般的な獣医師,平均的な獣医学の水準に達していたかどうか」で判断されます。
すなわち,上記判断基準に照らして,通常の獣医師であればおよそ予測不可能な容態の急変については責任を問われない(可能性が高い)といえます。
他方で,上記判断基準に満たない診療行為をした場合は,仮に手術承諾書などで,「如何なる事故が生じても獣医師は責任を負いません」といった免責条項を明記してもその責任を免れることはできません(最判昭43.7.16判時527号51頁)。
言わずもがなですが,獣医療学は日々進歩しており,「平均的な獣医療水準」も変わっていきます。医療事故を避けるという観点からも,獣医師一人ひとりが,日々の研鑽を怠らず,現在の獣医療水準に追いつく努力が,医療事故トラブルから自らを守る一番の予防策と言えます。
2. 裁判例

先日このHPでご紹介した「真依子ちゃん事件」(詳細はこちら)を一つの契機として,獣医療過誤事件の裁判例が増えてきておりますので,ご紹介します。
⑴ 獣医師に必要な検査をしなかった過失があるとして,慰謝料40万円を認めた事例
(東京高裁H120.9.26 判例タイムズ1322号208頁)
【事案】
飼い犬(ミニチュアダックスフンド。以下「葉子」という)が,無菌性結節性皮下脂肪織炎に罹患し,平成14年4月18日にA病院を受診したところ,同病院の獣医師らは,
①諸検査により葉子が免疫異常を原因とする無菌性結節性皮下脂肪織炎に罹患していることを診断し,本件犬に対し初診時以降1日当たり少なくとも8.6ミリグラムのプレドニゾロンを処方・投与すべきであったのに,これを怠り,
②葉子を,平成14年4月21日以降,B病院等の高次医療機関に転送すべきであったのに,これを怠り,
③初診時以降,葉子の疾患として「皮下脂肪織炎」の「疑い」があり,その原因として「免疫異常」が「考えられる」ことを説明すベきであったのに,これを怠った,
これらの各過失により,葉子の入院が長引いて,間質性肺炎及びDIC(播種性血管内凝固)を発症させ,B病院においてプレドニゾロンの大量投与を余儀なくさせるなどした結果,葉子に右前足を引きずる等の後遺障害を負わせるなどした事案
【判示要約】
1 獣医師は,準委任契約である診療契約に基づき,善良なる管理者としての注意義務を尽くして動物の診療に当たる義務を負担するものである。そして,この注意義務の基準となるべきものは,診療当時のいわゆる臨床獣医学の実践における医療水準である。この医療水準は,診療に当たった獣医師が診療当時有すべき医療上の知見であり,当該獣医師の専門分野,所属する医療機関の性格等の諸事情を考慮して判断されるベきものである。
2 初診時に,無菌性結節性皮下脂肪織炎の診断のため通常執られている手法に従い,生検を実施し,外部の検査機関に委託して菌の培養をし,無菌であるかどうかを確認するなどの措置を執るべき注意義務があったがこれを怠った過失がある。
3 被控訴人(飼い主【筆者補足】)は,葉子を平成2年からペットとして飼い始めたものであるが,葉子を我が子同様に可愛がり,強い愛着を抱いていたことは,葉子の治療に関して近くの動物病院で治療が効果を挙げないと,わざわざ自宅から離れた控訴人病院を受診し,さらに,入院中の葉子を見舞うため,A病院の近くのホテルにまで宿泊していたこと等からも十分うかがえるところである。ところが,葉子は,間質性肺炎及びDICに罹患し,一時生死が危ぶまれるような状態に陥ったのであり,入院期間も,B病院に転院して長引いたのである。また,葉子が重篤な状態に陥ったことが,退院後の通院治療等(その内容,頻度等)にも一定の影響を及ぼしていることが推認される・・・そして,これらのことにより,被控訴人は多大な精神的苦痛を被ったものと認められるのである。
そうすると,葉子が飼育動物にすぎないこと,本件は獣医師の過失により動物が死亡したという事案ではないこと等を考慮しても,被控訴人が被った精神的損害を慰謝するに相当な金額は40万円と認める。
(また,同裁判例では,獣医師の説明義務について以下のように述べています)
4 獣医師が自ら医療水準に応じた診療をすることができないときは,医療水準に応じた診療をすることができる医療機関に転医することについて説明すべき義務を負い,それが診療契約に基づく獣医師の債務の内容となるというべきである。
もっとも,動物の医療の分野においては健康保険制度が存在せず,医療費が高額になりがちなこと,動物とその所有者(診療契約上の委任者。以下「飼い主」という。)との関わり方は様々であること等(ペットとして飼育しているのか,畜産の目的で飼育しているのか等)からすると,動物の診療契約において要求される医療の内容は,飼い主の意向によって大きく左右される面があるものである。
5 このように動物の診療については,
①飼い主の意向により診療内容が左右される面があるから,獣医師は,飼い主に対して,診療内容を決定するに当たり(特に高額の治療費を要する治療をするなどの場面においては),その意向を確認する必要があるところ,意向確認の前提として,飼い主に対し,動物の病状,治療方針,予後,診療料金などについて説明する必要があるというべきである。
②動物の生命,身体に軽微でない結果を発生させる可能性のある療法を実施する場合にも,飼い主の同意を得る必要があるところ,その前提として上記のような事柄について説明する必要がある。
③副作用が生ずるおそれのある薬剤を投与するなどの場合には,悪しき結果が生ずることを避け,適切で的確な療養状況を確保するために説明義務(療養方法の指導としての説明義務)を負う。また,その他,飼い主の請求に応じ(民法645条参照),診療経過や治療の結果について説明義務を負う。
⑵ 手術後の輸血についての説明義務違反を認めた事例
(名古屋地裁H21.2.25)

【事案】
原告らが、「C」と名づけて飼育していたウェルシュコーギー犬(以下「C」という。)に関し,獣医師である被告との間で診療契約を締結して腹腔内陰睾丸腫瘍摘出手術(以下「本件手術」という。)を受けたところ,9月12日に死亡したことについて,
①輸血の準備が不十分であった,
②輸血態勢の整った他院への転院を怠った,
③骨髄吸引生検,骨髄コア生検の実施を怠った,
④敗血症に対する適切な投薬を怠った,
⑤治療内容及び安楽死の選択についての説明を怠ったとして,損害賠償を求めた。
【判示要約】
1 本件手術前において,被告及びA獣医師は,原告に対して,本件手術のみならず,術後の治療のためにも輸血が必要となるが,被告病院においてはいずれも血液を確保することができないことに伴う問題点について具体的に説明し,手術にあたっての輸血と治療としての輸血のいずれについても原告らにおいて準備して被告病院で治療行為を受けるか,他の病院で治療行為を受けるかの選択について,熟慮した上で判断できるよう,分かりやすく説明する義務があったというべきである。
しかし,前記認定事実に照らせば,本件手術前において,被告及びA獣医師は,原告X3に対し,本件手術をするために必要な血液を被告病院で確保できないため,原告らにおいて供血犬を用意する必要があることは説明したものの,Cの骨髄機能は本件手術によっても回復しない可能性が高く,術後に骨髄機能が回復しなかった場合には,治療としての輸血が継続的に必要となること,治療としての輸血は1か月に1回程度継続して行う必要があるが,Dからは必要な量を確保できないので,本件手術後は原告らにおいて独自に血液を確保するか,他の病院で治療を受けることが必要となることについて,分かりやすく説明したとは認めがたい。
2 原告が,輸血態勢の整った他の病院で,Cに治療を受けさせたとすれば,治療としての輸血が行われることにより,Cの重度の貧血の悪化を遅らせることができたものであるから,Cが,その死亡した時点においてなお生存していた高度の蓋然性が認められるというべきである。Cは,9月5日に治療としての輸血を受けながら,その僅か1週間後である9月12日に死亡したものであるが,9月5日の輸血量は100mlであって,十分な量ではないから,十分な量の輸血をしても9月12日時点で死亡した可能性があるとは推認できない。もっとも,Cは骨髄機能が回復できない以上,治療としての輸血を続ける必要があり,十分な量の輸血をしたとしてもどこまで生存できるかは不確定要素が多いこと(証人A),Cは既に高齢であったことを考慮すると,十分な量の輸血をしたとしても,Cの9月12日より後の生存期間は短いものであった可能性が高いというべきである。
したがって,被告の説明義務違反と死亡との間には,相当因果関係が認められる。
3. 医療事故トラブルを予防する方法
⑴ 手術承諾書の内容を工夫する

医療事故訴訟において要求される「一般的な獣医師の水準」を満たす説明義務を尽くしていることがわかるような表記にすることが肝要です。さらに言えば,手術承諾書は,飼い主に苦情を言わせないようにするため,ではなく,書面作成を通じて手術の内容を飼い主が理解し納得して,手術に同意してもらう,すなわちインフォームドコンセントツールとして,活用すべきものです。
このような観点からみると,
・病名,症状,
・手術名と内容
・麻酔の方法と麻酔によるリスク
・手術の必要性と手術しない場合の経過予測
・手術自体のリスク
・合併症リスク
・他の治療法とのメリットデメリットの比較
・予想される予後経過や後遺症
など漏れなく明記することが好ましいと言えるでしょう。
⑵ カルテを詳しく書く
飼い主にした手術内容の説明内容,手術の内容や術前術後の経過など詳細に記録しておきましょう。もし飼い主から訴訟を起こされるなどした場合,カルテの開示を余儀なくされることもありますし,病院側の過失を否定するために当時のカルテを提出する,ということも想定されます。後々のトラブルの際に重要な証拠となりますので,カルテは可能な限り詳細に(できれば第三者が判読可能なレベルの字で)書きましょう。
⑶ 常日頃から弁護士に相談できる体制をつくる

上記で述べたような適切な対応をしていても,医療事故を100%避けられるわけではありません。万が一トラブルが起きたらどのように対応すべきか,医療事故対応に詳しい弁護士にいつでも相談できるような仕組みづくり(顧問弁護士の活用)をしましょう。
4. まとめ
1 獣医師は患者(飼い主)に対して,善管注意義務を負う。
⇒一般的な獣医療水準を満たす医療行為を提供する義務
⇒飼い主が治療について適切な意思決定ができるよう,必要な情報を適切に説明する義務
2 獣医師は,善管注意義務に違反すると獣医師(病院)が損害賠償責任を負うことがある
3 医療事故トラブルを避けるためには以下の3つが重要
・獣医師及び病院全体の医療レベルを高める日々の努力を怠らない
・手術承諾書,カルテをちゃんと作る
・顧問弁護士を活用する